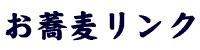
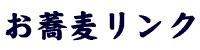 |
|
|
|
|
|
1.蕎麦について
|
|
日本においてそばの歴史は古く『続日本記』には、722年の飢饉の際に麦そばを植える命令がでたという記録があるそうです。ただ、一般的にそばを麺として食べるようになったのは江戸時代になってからということであり、その始まりは慶長年間(1596〜1615)に始まったといわれているようです。
そばの主材料はそば粉ですが、そば粉だけでは切れやすいため多くの場合は小麦粉などをつなぎに加えるようです。その割合は、そば粉8に対して小麦粉2がよいといわれており、江戸時代にはそば1杯が16文だった時期があり、二八そばと呼んでいたということです。 そばは、本来タデ科に属する一年生草本で、原産地は東アジアの温帯北部、バイカル湖から中国東北部といわれています。日本に中国から朝鮮を経て渡ってきたと考えられています。そばは冷涼な気候と痩せ地に適しており、稲の半分の育成日数で収穫されるため、山間部などの作物として日本では栽培されていました。 本来そばは穀物であり、それを加工していろいろな食べ物の材料として使ってきました。なかでも多くのひとになじみがあるのは麺としてのそば(そば切り)でしょう。 そば切りはそば粉よりつくられますがこのそば粉にも種類があり、更科粉、一番粉、二番粉、三番粉、末粉というものに分けられます。更科粉は、そばの外皮を取り除いて軽く引き割り、2〜3つに割れた大きなものだけをさらに細かくひいたものもです。ただし、軽くひいて胚乳の中心部だけが砕けた一番粉を含めて更科粉ということが多いようです。この更科粉を使って白く甘味のある上品な「更級そば」というものがつくられる。また、ひきぐるみという殻を取った後に三番粉になるまでひいた黒っぽい粉で作った香りの強い麺を「田舎そば」といいます。 有名なそばとしては、島根の出雲そば、長野の戸隠そば、徳島の祖谷(いや)そば、新潟の十日町そば、兵庫県の出石(いずし)そば、岩手のわんこそば、などが有名です。 そばは健康食品といわれ、ビタミンB類(ビタミンB1、B2)や、血管を強くするルチンが含まれるが、茹でると栄養物は溶け出すので、ゆで汁にも栄養物が含まれている。したがってそば湯を飲むことにも理由があるのです。 そばはそば切り(麺の状態)にするだけではなく、熱湯を注いで蕎麦がきしにて、ねぎや大根おろしなどの薬味を添えて醤油などをつけて食べられます。この他にもそばボーロ、そば饅頭、落雁などのお菓子にもつかわれる。また、韓国・朝鮮料理の冷めんや、ヨーロッパではクレープなどの材料にも使われています。それにお酒では焼酎の原料になっています。 |